快適な職場環境をつくるための温度や湿度の管理基準を徹底解説
従業員の健康管理に関わる要素の一つに、職場の室温管理が挙げられます。ただし快適と感じる温度・温度には個人差があるほか、新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)の感染対策として、こまめな換気を行うことも必要です。本記事では、『事務所衛生基準規則』で定められた室温の基準をはじめ、快適な職場環境をつくる室温管理のポイントを解説します。
記事を見る従業員の健康管理に関わる要素の一つに、職場の室温管理が挙げられます。ただし快適と感じる温度・温度には個人差があるほか、新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)の感染対策として、こまめな換気を行うことも必要です。本記事では、『事務所衛生基準規則』で定められた室温の基準をはじめ、快適な職場環境をつくる室温管理のポイントを解説します。
記事を見る従業員の健康状態を把握して健康保持に努めるために、企業には健康診断の実施が義務付けられています。本記事では、健康診断の義務や種類、実施の目的について解説します。
記事を見る従業員数が多い会社では、健康診断の実施までに伴うさまざまな手続き・事務作業が煩雑になりやすいです。なかには、「どのように予約や準備を進めればよいか分からない」という方もいるのではないでしょうか。この記事では会社で健康診断を実施する際の流れと注意点について解説します。
記事を見る従業員にコロナ感染の疑いがある場合は、企業は適切に医療機関等での検査を促したり、感染者が出た際の対応を行ったりします。しかし、海外渡航の前後などでも、検査が必要となる場合があります。この記事では、企業でPCR検査を実施する流れをはじめ、感染者が出た場合の対応や保健指導について解説します。
記事を見る健康経営に関する制度について、経済産業省では健康経営に積極的に取り組む企業を評価するための “ホワイト500”という認定制度を設けています。ホワイト500の認定を目指しているものの、「基準や認定までの流れが分からない」という企業もあるのではないでしょうか。この記事では、ホワイト500の認定基準や申請手続きについて解説します。
記事を見る女性が妊娠・出産というライフイベントを迎えるときは、身体に大きな変化が起こり、精神的な負担にもつながりやすくなります。 事業者には、女性従業員の健康を守り、安心して妊娠・出産を迎えられるように、妊婦さんに配慮した職場環境を整備する“母性健康管理”が義務づけられています。 この記事では、出産・育児に関する休業制度をはじめ、妊娠中の従業員に対して人事・労務部門が行う対応や注意点について解説します。
記事を見る1日の多くを過ごすオフィスは従業員の健康に与える影響も少なくないと考えられることから、“健康経営オフィス”という考え方も広がりを見せています。この記事では、健康経営オフィスとは何か、また健康で快適な職場環境をつくる7つのポイント、取り組みの注意点について解説します。
記事を見る物流業界の“自動車運転の業務”においては、5年間の猶予期間が設けられており、2024年4月1日から規制が適用されます。 しかし、トラックドライバーが不足している企業は増加傾向にあり、時間外労働の規制が適用されることで諸問題が生じると懸念されています。 物流業界において労働時間の上限規制が適用される2024年に向けて、物流業界各社は働き方改革への対応を迫られており、規制適用に関する諸問題は「2024年問題」と呼ばれています。 物流会社の人事・総務担当者の方は、働き方改革の改正ポイントを踏まえたうえで、2024年問題に向けて対策を始めることが重要です。 この記事では、物流業界の2024年問題の概要をはじめ、法改正のポイントや取り組み例について解説します。
記事を見る近年では、新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)の拡大によって生活習慣や働き方が変わったことで、運動不足や生活習慣病などによる健康二次被害が懸念されています。 企業においては、従業員の健康不安を解消するために、健康維持・増進に向けた取り組みが重要です。 この記事では、健康強調月間の目的をはじめ、具体的な取り組み内容・事例について解説します。
記事を見る生活習慣病の予防を目的として、高齢者の医療の確保に関する法律(以下、高齢者医療確保法)の第20条では、特定健康診査(以下、特定健診)の実施を義務づけています。特定保健指導とは何か、また企業で実施する際の進め方について解説します。
記事を見るクラウド型健康管理サービス「first call」は、
人とシステムの両方で、企業の健康管理をサポートします。

企業の健康管理にお悩みの方は、お気軽にご相談ください

サービス資料
クラウド型健康管理サービス「first call」の特徴を知りたい方は資料をダウンロードください。
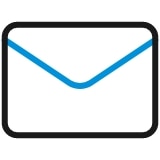
お問い合わせ
お悩みや不安点、サービスの詳細を確認したい等、お気軽にお問い合わせください。