うつ病で周りが疲れる職場の原因とは?会社がすべき支援や対策を解説
うつ病の社員がいる職場で、周囲の人が疲弊してしまうのには、いくつかの理由があります。この記事では、なぜうつ病の社員がいると周りが疲れてしまうのか、その根本的な原因を分かりやすく解説していきます。
記事を見るうつ病の社員がいる職場で、周囲の人が疲弊してしまうのには、いくつかの理由があります。この記事では、なぜうつ病の社員がいると周りが疲れてしまうのか、その根本的な原因を分かりやすく解説していきます。
記事を見る化学物質リスクアセスメントとは、事業場で使っている化学物質の「危険性」や「有害性」を把握し、それが労働者にどのくらい危険な状況なのかを評価することです。この記事を読めば、なぜ今この取り組みが重要なのか、法令の改正で何が義務になったのか、そして「明日から具体的に何をすればいいのか」がはっきりとわかるはずです。
記事を見るポピュレーションアプローチとは、簡単に言うと「従業員みんなで健康になろう!」という考え方です。健康経営を成功させるための、効果的な手法のひとつが「ポピュレーションアプローチ」です。この記事では、ポピュレーションアプローチがどのようなもので、なぜ企業にとって大きなメリットがあるのかを詳しく解説します。
記事を見るうつ病のサインは、一度きりの出来事ではなく、継続的な変化として現れることが多くあります。この記事では、うつ病のサインにいち早く気づき、適切に支援するための具体的な方法を解説します。
記事を見るうつ病など心の不調による1回目の休職は、平均で107日(約3.5ヶ月)という結果が出ています。2回目の休職となった場合は、平均157日(約5.2ヶ月)と、期間が長くなる傾向があります。この記事では、従業員のうつ病による休職に直面した際に自信を持って対応できるように詳しく解説します。
記事を見る衛生委員会ではテーマの決め方や議題の進め方といった方法を少し工夫するだけで、もっと活発で意味のある活動に変わります。この記事では、明日から使える衛生委員会のテーマに関する年間事例から、効果的な議題の決め方、マンネリ化を防ぐための対策まで、幅広く解説していきます。
記事を見る健康経営アドバイザーは、一言でいうと「社内の健康経営を盛り上げるリーダー」のような存在です。この記事では、健康経営アドバイザーがどのような役割を担うのか、資格を取得することで企業や担当者自身にどのようなメリットがあるのか、そして資格取得の具体的な方法や試験の概要まで、わかりやすく解説していきます。
記事を見る安全管理者と衛生管理者の最も大きな違いは、その役割にあります。この記事では、安全管理者と衛生管理者の役割や仕事内容、選任の条件といった基本的な違いから、資格の取得方法、兼任はできるのか?といった気になるポイントまで、わかりやすく解説します。
記事を見る「安全衛生」とは、一言でいうと職場における労働者の安全と健康を確保し、誰もが気持ちよく働ける快適な職場環境の形成を促進するための活動全般を指します。この記事では、そんな「安全衛生」の基本から網羅的に解説します。
記事を見るストレスマネジメントとは、「原因」と「反応」の間に上手く介入して原因を減らしたり、つらい反応を和らげたりするための工夫や方法のことです。この記事では、ストレスマネジメントの基本的な知識から、個人で今日からすぐに試せる具体的な方法、そして企業ができる支援や組織としての取り組みとその効果まで、分かりやすく解説していきます。
記事を見るクラウド型健康管理サービス「first call」は、
人とシステムの両方で、企業の健康管理をサポートします。

企業の健康管理にお悩みの方は、お気軽にご相談ください

サービス資料
クラウド型健康管理サービス「first call」の特徴を知りたい方は資料をダウンロードください。
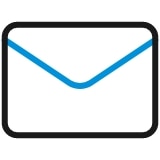
お問い合わせ
お悩みや不安点、サービスの詳細を確認したい等、お気軽にお問い合わせください。