産業医はどこにいる?探し方から選任する方法、料金相場や相談先を選ぶポイントを解説
産業医の探し方は、産業医紹介会社、地域の医師会、健康診断機関、地域産業保健センター、の主に4つです。この記事では、産業医がどこにいるか詳しく解説しています。
記事を見る産業医の探し方は、産業医紹介会社、地域の医師会、健康診断機関、地域産業保健センター、の主に4つです。この記事では、産業医がどこにいるか詳しく解説しています。
記事を見る産業医とは、事業場において労働者の健康管理等を行う医師のことを指します。労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任が義務付けられています。産業医の役割や仕事内容、企業にとっての必要性などについて、わかりやすく解説します。
記事を見る従業員数・業務内容によって、必要な産業医の数や、嘱託または専属のどちらの産業医を設置するかといった条件が異なるため、要件について正しく理解しておくことが重要です。 この記事では、必要な産業医の人数を、産業医の要件とともに解説します。産業医の管理にお悩みの方は、ぜひご一読ください。
記事を見る産業医を派遣してもらうためには、主に産業医を派遣しているサービスを利用します。このサービスを通じて、企業は労働者の健康管理を担当する産業医を確保できます。本記事では、産業医を派遣してもらう方法について、産業医派遣の仕組みや主な依頼先、費用相場、そして産業医の業務内容まで、幅広く解説します。
記事を見る産業医として選任できるのは、医師のうち、所定の養成研修・講習を修了した人などに限られます。現在では産業医資格を取得している医師は約10万人以上(全医師のおよそ1/3程度)いますが、そのうちの実働は推計約3万人にとどまっている状況です。 事業場でいざ産業医を選任しようとした際に、「産業医とどのように出会えばよいのか」「選任する際の注意点は何だろう」と悩まれるケースもあるのではないでしょうか。 この記事では、産業医を紹介してもらう一般的な方法や、選任する際の注意点について解説します。
記事を見る産業医とは、事業場における従業員の健康管理を行う医師のことです。普段は病院で勤務しながら、企業で産業医として活動する医師がほとんどですが、産業医としての活動と医療機関での医師の活動とは異なる点があります。 この記事では、産業医の認定要件と、産業医と医師の違いについて解説します。
記事を見る産業医は、メンタルヘルスに関する専門的な知識と経験を持ち、ストレスチェックの実施から面接指導、集団分析まで、労働者の心身の健康確保のために重要な役割を持っています。この記事では、ストレスチェック制度における産業医の役割について詳しく解説します。産業医がストレスチェックの実施者となることのメリットや、実際の運用における産業医の関わり方について、具体的に見ていきましょう。
記事を見る専属産業医の1年間の報酬は「300万円〜400万円×週の勤務日数」が目安です。嘱託産業医の報酬は、事業場の労働者数に応じて設定されることが一般的です。産業医の報酬の相場について、目安となる金額や報酬に差が生まれる要因などを詳しく解説していきます。
記事を見る常時50人以上の従業員を雇用する事業場には、産業医の選任義務が課せられます。産業医は、事業場における従業員の健康管理全般に関する責任を負っており、業務内容は法律によって細かく定められています。 この記事では、産業医の業務内容や産業医へ相談できる内容を解説します。
記事を見る職場環境改善に大切なのは、会社の状況に合った施策を選ぶこと。この記事では、職場環境改善の具体的な進め方から、よくある失敗とその対策まで、実践的なノウハウをご紹介します。
記事を見るクラウド型健康管理サービス「first call」は、
人とシステムの両方で、企業の健康管理をサポートします。

企業の健康管理にお悩みの方は、お気軽にご相談ください

サービス資料
クラウド型健康管理サービス「first call」の特徴を知りたい方は資料をダウンロードください。
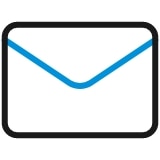
お問い合わせ
お悩みや不安点、サービスの詳細を確認したい等、お気軽にお問い合わせください。