優秀な人ほど辞める会社の特徴や退職前のサインを解説
なぜ優秀な人は会社を辞めてしまうのでしょうか?給料が低い、成長できない、仕事が多すぎるなど、様々な理由があります。会社の将来に不安を感じたり、人間関係で悩んだりすることもあるでしょう。優秀な人が辞めないようにするには、これらの理由をよく知ることが大切です。
記事を見るなぜ優秀な人は会社を辞めてしまうのでしょうか?給料が低い、成長できない、仕事が多すぎるなど、様々な理由があります。会社の将来に不安を感じたり、人間関係で悩んだりすることもあるでしょう。優秀な人が辞めないようにするには、これらの理由をよく知ることが大切です。
記事を見る優秀な人材の早期退職は、業務の質の低下だけでなく、他の社員のモチベーション低下にもつながり、会社全体に大きな影響を与えてしまいます。この記事では、優秀な人材の見切りが早い理由や、退職前の行動の特徴、そして具体的な防止策について解説します。
記事を見る従業員から適応障がいであることを申告された場合、本人の健康状態の回復、そして労働災害や従業員とのトラブルを防ぐためにも、企業として適切な対応を取る必要があります。この記事では、適応障がいとは何か、また企業としての対応や適応障がいを防ぐための対策について解説します。
記事を見る新入社員の入社や転勤など、職場環境が変わることの多い4月。新しい環境に少しずつ慣れてくる5月に入ったあたりから、心身に不調を感じる“五月病”の症状が現れる従業員も少なくありません。五月病は一過性の症状といわれていますが、仕事に対するやる気の低下によって、会社にもさまざまな影響を及ぼす可能性もあります。場合によっては離職につながることもあるため、人事・総務の担当者には適切な対策が求められます。この記事では、五月病の原因やなりやすい人の特徴、企業における対策について解説します。
記事を見る部下が心身の不調で働くことが困難になった場合、休職の申出を受けることがあります。 日頃の業務で関わりの深い上司にとってはつらいことですが、企業としては症状が深刻化する前に療養を促して、職場復帰に向けた支援をしていくことが大切です。 また人事・総務担当者は、休職者の上司に対して、対応方法を共有したり、場合によってはどう対応すべきか指示したりする必要があります。また、休職を予防するような仕組みづくりも求められます。 この記事では、部下が休職することになった際の上司に求められる対応と、休職者を出さないためのポイントについて解説します。
記事を見る人材の流出や労働災害を防ぐためには、心の健康問題によって休業した従業員に対する、企業の適切な職場復帰の支援が重要です。この記事では、休業した従業員の職場復帰を支援するプログラムの基本的な取り組みや流れについて解説します。
記事を見る厚生労働省は、適切なメンタルヘルス対策を行うために必要な取り組みとして“4つのケア”を示しており、そのうちの1つに“セルフケア”という項目があります。 「セルフケア」とは、私たちが自分自身で行うことのできるケア。働く人が自らのストレスに気付き、予防対処し、また事業者はそれを支援することで、事業者は労働者に対して、次に示すセルフケアが行えるように教育研修、情報提供を行うなどの支援をすることが重要です。 しかし、「従業員にセルフケアを促したいけれど、どうしたらよいか分からない」「セルフケアの具体的な方法を知りたい」といった人事・総務担当者の方もいるのではないでしょうか。 本記事では、セルフケアについて具体的な取り組み事例とともに解説します。
記事を見る2015年12月以降、労働安全衛生法の改正によってストレスチェックの実施が義務付けられました。ストレスチェックにより、従業員のストレスがどのような状態にあるかを把握できます。うつ病を含むメンタルヘルス不調の未然防止に役立つ制度です。本記事では、ストレスチェックの基本概要、実施の流れ、注意点を分かりやすく解説します。
記事を見る企業において、日々業務に励む従業員のなかには、職場環境や家庭環境など、さまざまな要因でストレスを抱えている人も少なくありません。 メンタルヘルス不調の深刻化を防ぐためには、不調のサインに早く気づいたうえで、適切な対処を行うことが大切です。日ごろ直接関わる機会の多い上司は、そういった従業員のサインにいち早く気づき、対応することが求められます。 この記事では、メンタルヘルス不調を起こしている際にみられるサインや、上司に求められるメンタルヘルス不調の対処法を紹介します。
記事を見る企業で働く従業員の健康を保持・促進するための制度として、ストレスチェックの実施に活用できる助成金があります。実施に関しては、常時従業員50人未満の事業場においては努力義務とされていますが、従業員の健康管理を適切に行うためには実施が望まれます。本記事では、ストレスチェックを実施する際に活用できる助成金の受給要件や申請方法、注意点について解説します。
記事を見るクラウド型健康管理サービス「first call」は、
人とシステムの両方で、企業の健康管理をサポートします。

企業の健康管理にお悩みの方は、お気軽にご相談ください

サービス資料
クラウド型健康管理サービス「first call」の特徴を知りたい方は資料をダウンロードください。
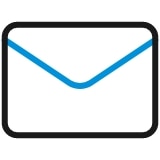
お問い合わせ
お悩みや不安点、サービスの詳細を確認したい等、お気軽にお問い合わせください。